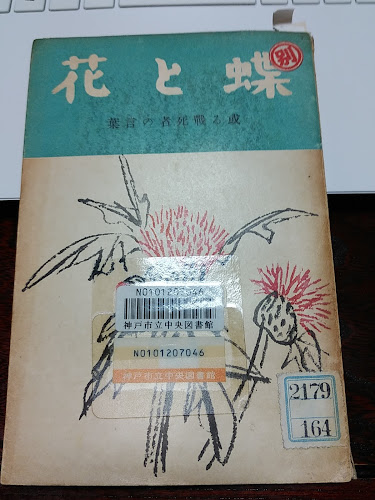「空の青さがほんとうにわかれば…」 戦争と「弔い」と(6)
(前回のつづき) ここまで、太平洋戦線の激戦地を回る「慰霊ツアー」のなかで、参加者たちの慰霊の仕方に見られる、差異が意味していることについて、赤松と彦坂の対話をとおして考えてきた。 では、赤松は、彼にとってのツアー目的地であるガ島に上陸し、そこで何を確かめたのだろうか。ガ島に向う船中で、赤松は彦坂に次のように語っている。 「上陸時の(米空軍機との)戦闘ではね、波が少しあって、そして、海の色は、もう真っ青! …ブルーですよ。…(夕方になると)海もあかるなるってるし、兵隊の顔もみんな染まっている、その色に。…空の色やら水の色なんかは、ほんとうに、もう、ぼくだけのものなんだなあ…。戦記を書く人も、その戦闘を記録する人も、そういうことは…(書かないんだ)。」 「そのときの空の色や水の色と関係のない戦争とね、そういうものと結びついて離れない戦争とね、同じ戦争といっても、二つの戦争が考えられるねえ。 …つまり個人的戦争にはね、空の色も水の色もね、入ってんですね。…その個人にとっての戦争を代表する人たちっていうのはね、(軍隊の)一番下の人たちで、…だんだん階級が上がっていくとね、…もうかけらのないわけよ、個人的戦争の色彩は。」 慰霊ツアーの船がガ島に着き、下船した赤松は、慰霊団とは別行動をとり、彦坂とともにかつての上陸地点へまっすぐに向かった。 「42年前、餓死寸前の身体をただ気力だけでもたせながら、迎えの駆逐艦が来てくれるはずの海岸を目ざして這って通った、その草原」も、「飢えと渇きと、とめどのない下痢と高熱に悩まされながら、一粒のコメももらわずに過ごしたあの密林」も、かつてのようにはなかった。40余年の年月が流れていた。赤松は、そこでとくに慰霊的な行為、たとえば日本から持ってきた酒とかタバコとかを供えるようなことをしたわけではない。すっかり姿を変えたそれらの場所を歩き回ったあと、草原にごろりと横たわった。たぶん、衰弱し身動き一つできず密林の中で横たわっていた、あの時の姿勢のように。のちに、再訪したその場で赤松が思ったことを彦坂に次のように語っている。 「 …あそこで(上陸地点を再訪することで)ぼくが直面したのはね、(あの)世界で生きることはもう不可能だということやったんや。その世界はもうないけど、ぼくは生きていかんならんということやったんや。その思いを...